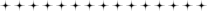※冒険行編【5】です。一覧は
こちらから
誰かに何かを囁かれたような気がして、スリジエの意識は覚醒した。重い瞼を擦って薄らと目を開けると、部屋の中はまだ暗かった。窓から差し込む月明かりだけが、今この部屋で確認できる唯一の光だった。
「ん……。」
背中にいつも通りの温もりを感じるが、いつものように抱き締められてはいないようだ。そっと身体を起こして隣で眠るミシェルの様子を伺う。顔を覗き込んでも瞳は閉じられていて、規則正しい寝息が聞こえるだけだったので当然眠っているようだ。
改めて耳を澄ましてみるが、聞こえるのは自分たちの呼吸の音と、外から聞こえる木々のさざめきや虫の声だけだ。
確かに何か意志を持ったものに囁きかけられた感覚があったのに、夢だったのだろうか。
気の所為ならそれでいいやと、スリジエはもう一度ベッドに横になってミシェルの温もりを感じながら眠りについた。
++++++++++
「夜中に声が聞こえた、か……。」
愛羽の手綱を引きながら、ミシェルはふむ、と考える。
「うん。でも、夢か気のせいかも。」
一方スリジエは今日もチョコボの背に揺られながら、前を歩いて先導するミシェルの背を眺めていた。時刻は昼前、まだ朝の名残を感じられる森の空気が清々しい。
「気の所為とも限らないよ。黒衣森には精霊がいるというし、もしかしたら彼らかもね。」
精霊とは、一般的には黒衣森に住まい、森を護っているとされる存在である。それらは地神ノフィカから分かたれたものだとされ、森都グリダニアではポピュラーな話題らしい。そんな精霊信仰の事情は隣国であるイシュガルドにまで噂が届き、ミシェルも聞き覚えがあった。
グリダニアでは、精霊の声を聞くことは幻術を修めた道士の役割だという。それならば、幻術の才があると思しき者に精霊の声が聞こえてもおかしくはないだろう。
「でも、今まで聞こえたことないよ?」
「そりゃあ、イシュガルドで精霊が何かしたなんて話なんて聞かないしね。そんなに活発じゃないんじゃないかな。」
そんな説明を聞いても、スリジエは納得がいかなかった。何故なら、むかし黒衣森で暮らしていた頃だって、精霊の声なんて1度も聞いたことがなかったのだから。
今だって、こうして森の中にいるが何も聞こえない。ただ、ほんの少しの懐かしさを感じるだけだ。
チョコボの背でどことなく不服そうにしているスリジエをちらりと振り返り、ミシェルはふっと笑う。
「そんなに気になるのなら、グリダニアに着いたら幻術士ギルドを訪ねてみたらいいさ。」
「ん、わかった。」
ミシェルの言う通り、専門家に訊くのが間違いないだろう。そう納得してスリジエは考え込むのをやめて前方を見据えた。茂る木々の向こうには森都の門が見えていた。
++++++++++
2人が歩いてきた北部森林と呼ばれる地域からグリダニアへと入る門は、黄蛇門というらしい。その門から都市内へ入ったところで、スリジエはぽつりと呟いた。
「ミシェルって、なんだか詐欺師みたい。」
やれ、自分はイシュガルドで傭兵をやっていただの、傭兵から冒険者に転向する為に来ただの、連れは知り合いの子で冒険者登録の為に付き添ってきただの。門番を務める兵士相手ににこやかに笑いながら、次から次へとでまかせが出てくるのだ。
「嘘も方便というやつさ。こういう時は詮索される前にそれらしい事をこちらから話してしまう方がいい。」
こともなげに飄々と言うミシェルに、スリジエは呆れを通り越して尊敬してしまった。こういうのを、世渡り上手というのだろうか。
「僕にはそういうの、絶対にむり……。」
ミシェルのように話上手だったら、もっと役に立てる事もあるかもしれないのに、と。そんなふうに落ち込みかけたスリジエの背を、ミシェルの手が優しく叩いた。
「素直なところがスリジエの美点だよ。」
励ますと共に歩みを促すように、その手が背中を押す。
「さあ、まずは冒険者ギルドへ行こうか。」
このグリダニアという都市は余所者への風当たりがきついらしい。下手に都市内を彷徨いて治安維持の兵士らに詰問されたくなければ、真っ先に冒険者登録を済ませに行け、とは先ほど黄蛇門で話した兵士の言である。
エレゼンとミコッテという組み合わせならば現地の人間に見えなくもないだろうが、不安要素は早く取り除くに越したことはない。
街並みを眺めるのもそこそこに、2人は標識を頼りにグリダニア新市街のほうへと歩いていったのだった。
++++++++++
建物に入り天井を見上げたスリジエは、ほう…と溜息をつく。頭上には1面のステンドグラスが陽の光を通して煌めいていた。
「……お茶の香り、いい匂い。」
「冒険者ギルドというから酒場を想像していたけれど、カフェのようだね。」
丁度昼時だったこともあり、茶房カーラインカフェの客席は賑わっていた。
フロアの奥にはカウンターが並びそれぞれに人が立っている。どれがギルドの担当者だろうかと入口で立ちつくしていると、こちらに気付いたカウンターのエレゼン族の女性が手招きした。
「やあ、見ない顔だね。冒険者かな?」
「ああ、どうも。貴女がギルドの顔役で?」
女性の方へと歩いていくミシェルに続きながら、綺麗な人だなあとスリジエは思った。ミステリアスな物腰は例えるなら、そう、魔女のようだ。
「僕はミューヌ、ここカーラインカフェで店主をやりながら冒険者ギルドの顔役もやらせてもらってるよ。」
ミューヌと名乗った彼女は、カウンターの上に一冊の本を取り出した。頁を開いてこちらに向けられたそれが、どうやら冒険者の名簿らしい。一緒に差し出されたペンで名前を書くようにと促されたミシェルが、そこにフルネームを書く。不要な詮索を避けるために、もちろんイシュガルド貴族特有の苗字の前に付く不変化詞は省いて、だが。
「ミシェル・ラグランジュ、いい名前だね。その装備からして素人には見えないけれど、これまでは何を?」
「イシュガルドで騎士団に所属していてね。扱き使われて嫌気が差したから冒険者に転向しようと思ってここまで来た次第さ。」
それは腕が立ちそうだ、とミューヌが頷く。そして彼女はスリジエへと視線を移すと、ペンを差し出した。
「初々しい君も冒険者になるんだよね?ここに名前を書いておくれ。」
ペンを受け取り、どうしたものかとスリジエは考える。自分の名前はスリジエ。フルネームを記すならば、じゃあ苗字は?
昔の名前はきっと安否不明か死亡の扱いになっているだろうし、その頃の苗字を使うと、もしかしたら何か厄介事に発展する可能性もあるかもしれない。種族や地域によっては苗字を持たない人というのもいると聞いたことがあるから、名前だけでもいいのかもしれない。
ちらりとミシェルを見上げると、なかなか名前を書かないスリジエを心配そうに見下ろしていた。
先に書かれたミシェルの名前を見る。現状で自分はミシェルの被保護者のようなものだ。じゃあ、この人の苗字を貰ってしまってもいいのかな、なんて。
「……スリジエ・ラグランジュか、エレゼン風の名前だね。ああ、いや、別に詮索はしないとも!君もいい名前だね。」
ペンを置いてミューヌの言葉にこくりと頷く。ミシェルに付けて貰った大切な名前を、いい名前だと言われるのは嬉しかった。
もう一度ミシェルのほうを盗み見ると、唇を引き結んで何か感情を耐えているような、なんとも言えない顔をしていた。その顔はいったいどういう気持ち?
「さて、君たちがグリダニアでやっていくにあたって知っておくべきことを説明しようか。」
++++++++++
エーテライトのこと、商店街のこと、幻術士ギルドのこと、それから店内に常駐している冒険者指導教官のこと、冒険者ギルドに併設された宿屋とギルドリーヴの窓口のこと。一度に沢山の事を説明されて目を回すスリジエに、ミシェルは苦笑する。
「説明ありがとう、ミューヌ。では早速街へ散策へ……と行きたいところだけど、僕達は昼飯がまだでね。お勧めがあればそれを貰えるかな?」
「ああ、いいとも。そっちのテーブルに掛けて待っていておくれ。」
指し示された空いているテーブルに2人は腰掛けた。やや疲れた様子のスリジエは、先程の説明で頭がいっぱいなのか、どこか上の空だ。
「大丈夫?今日はもう休むかい?」
「ううん、だいじょうぶ。」
「そうかい?無理はしたらいけないからね。」
本人は大丈夫だというが、数年間の軟禁生活からのこの決死行だったのだから、とうにへとへとの筈だ。よくよく様子を見ているようにしようとミシェルは心に誓った。
「お待たせしました!当店名物のラプトルシチューとハーブティーです!」
給仕係のミコッテ族の女性が愛想よく料理を配膳してくれる。テーブルの上に置かれた木製のボウルにたっぷりとよそわれたシチュー。具材がごろごろと入っているそれからは、湯気が立っていて実に美味しそうな匂いがする。別の皿に盛られたパンも合わせればなかなかのボリュームだ。
ティーカップからは複数のハーブがあわさった爽やかな香りが漂ってくる。
先程までぼんやりしていたスリジエも耳をぴんと立てて、視線はすっかりシチューに釘付けになっていた。
「それじゃあ、いただこうか。」
弾むような足取りでカウンターへと戻って行く給仕を見送り、ミシェルも料理へと向き直る。
「ん、いただきます。」
とろみのついたスープをひとさじ掬って、少し冷ましてから口にする。思いのほか素朴な味付けが、疲れた身体に染み渡る。良く煮込まれたラプトルの肉は柔らかく、味は鶏肉に近い。
他の具材はミシェルにとって食べた事がない味だったが、食感からして恐らくキノコだろうか。
「美味しいけれど、この具、キノコかな……なんというものだろう。」
「……たぶん、シャンテレール?こっちはギルバン、だと思う。」
思ったままの疑問を口にすると、意外なことにスリジエがそれに答えた。
「へえ、詳しいね。ありがとう。」
「ん。」
イシュガルドには流通していない食材だが、グリダニアではメジャーな物なのだろうか。そしてスリジエはそれを知っていたことから、スリジエはやはり黒衣森で暮らしていたことがあるのだろうと、ミシェルは推察する。
知らなかった一面が垣間見えたことが、少し嬉しい。そんなことを思いながら横に座るスリジエを見ると、スプーンに掬った肉に執拗にふーっと息を吹きかけて冷ましていた。猫舌なのは相変わらずだ。
「……あちっ、」
「ふっ、大丈夫かい?ゆっくり食べなさい。」
スリジエが肉の塊を頬張って、熱そうにはふはふと咀嚼している様子に、ミシェルは思わず微笑んでしまった。
初めての土地で目に映るものはどれも新鮮だが、過ぎる時間は穏やかだ。凪いだ心には、まるで命からがらの逃亡劇が遥か過去の事のように感じられた。
この調子なら、きっとこの先も何とかなるだろう。根拠もなくそんな風に考えながら、ミシェルは温かなハーブティーを一口飲み下した。
地位や名誉から逃れ、ただ自由を求めて。斯くして、実に平凡な冒険者という立場になった二人の旅は、この森の都グリダニアから始まる。
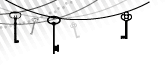
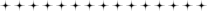
 (03/05)アリストクラットの愛猫_33
(03/05)アリストクラットの愛猫_33 :0
:0